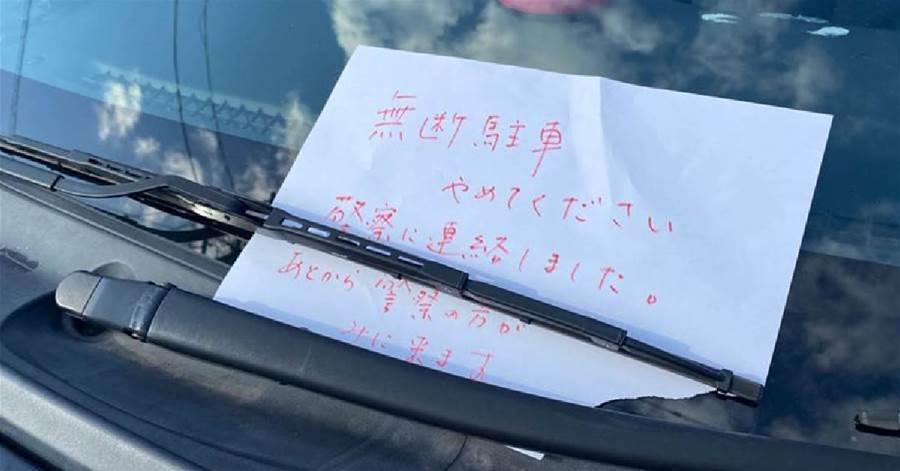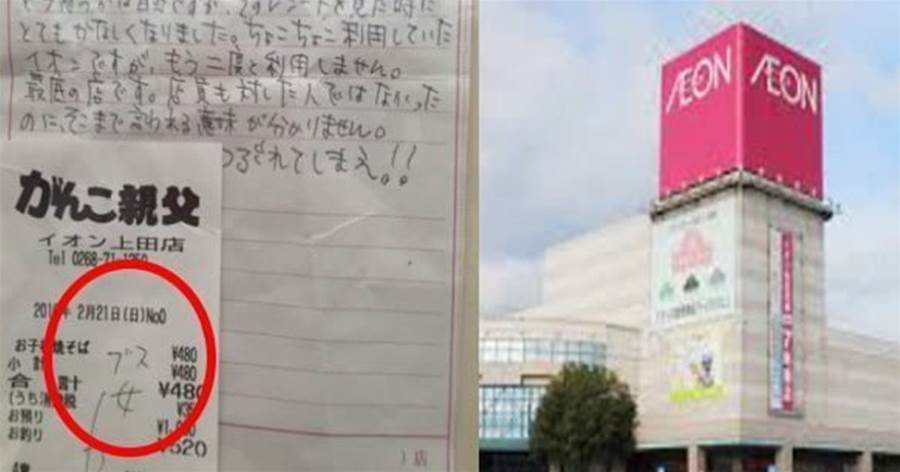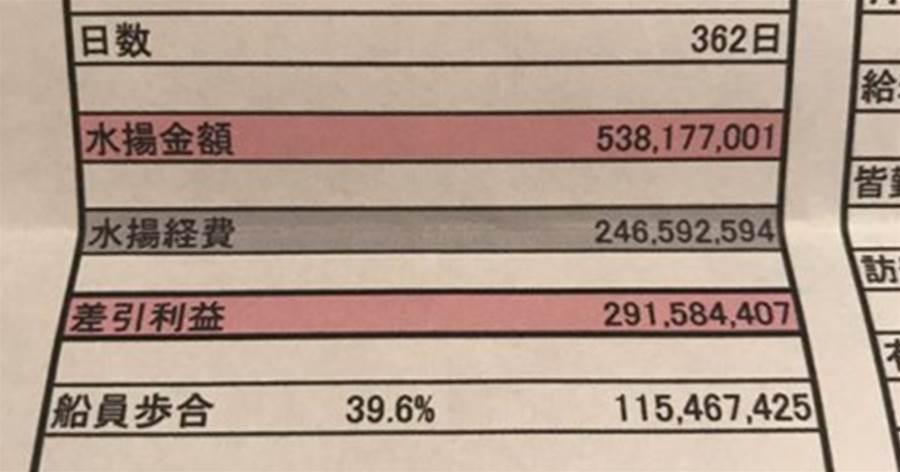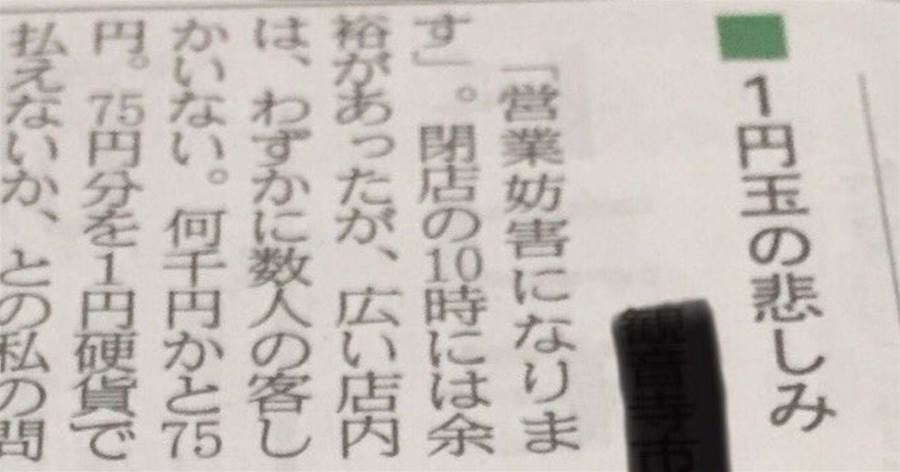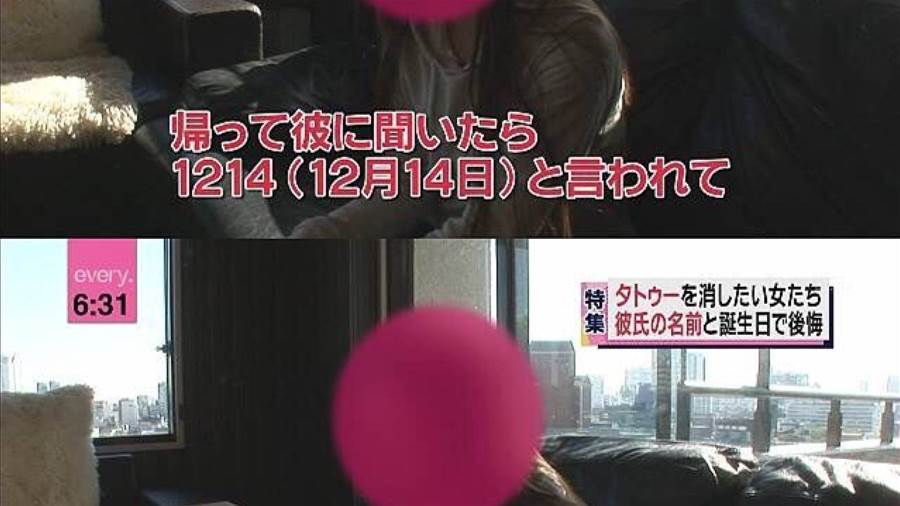新入社員を教育するのは大変なことですが、特にゆとり世代の新入社員を指導するのはさらに大変です。ある日、新入社員に買い物に行ってもらったところ、予想外の結果が起こりました。上司から2,000円を渡され、「普通の牛丼を人数分買ってきてほしい」と頼まれた新入社員は、元気に了承しました。しかし、帰ってきた新入社員は「2,000円では足りなかったので、自腹で足して買ってきました!」と言い、袋から取り出した牛丼は全部特盛りでした。
上司は驚きつつも「ご苦労さん」と労いましたが、新入社員は「普通の牛丼と言われたから特盛りを買ってきた」と主張しました。この出来事から、言葉の認識の違いがトラブルの原因となる可能性があることが示唆されました。

ネット上では、普通の牛丼とはトッピングのないものとも受け取れるという意見や、自腹で特盛りを買う選択肢が理解できないという意見がありました。また、指示が曖昧な上司や、食事の際にもやんわりと指摘できる有能な新人社員に対する称賛の声も上がっています。
この出来事は、コミュニケーションの不足や誤解がトラブルを引き起こす可能性があることを示しています。先輩社員と新入社員が同じ言葉を異なる解釈で受け取ることがあるため、今後も同様のトラブルが起こる可能性があることが懸念されます。

ネットから上記の内容への見解:
この「牛丼事件」は、一見すると些細なコミュニケーションミスのように思えますが、現代社会に潜む根深い問題を浮き彫りにしています。それは、**「指示待ち人間」と「忖度疲れ」の蔓延**です。
新入社員は「普通の牛丼」という指示に対して、自ら「特盛」という選択肢を提示することなく、言われた通りに実行しました。これは、指示された範囲内でしか行動できない、思考停止状態とも言えます。自ら考え、行動する主体性や、状況に応じて柔軟に対応する能力が欠如している点は、現代の若者の傾向として危惧すべき点です。
一方、上司は「普通の牛丼」という曖昧な表現を用いながらも、新入社員が自腹を切ってまで特盛を買ってきたことに対して、「ご苦労さん」と労うのみ。これは、指示の甘さを棚に上げ、問題の本質から目を背けているとも言えます。
現代社会では、上司は部下に明確な指示を出すことを避け、部下は上司の意図を過剰に忖度することが横行しています。
その結果、誰も責任を取ろうとせず、問題が先送りされるという悪循環に陥っているのです。
今回のケースでは、上司が「予算は2,000円で、全員分の普通の牛丼を買ってきてほしい。もし予算が足りない場合は、私に相談して」と具体的に指示を出していれば、このような問題は発生しなかったでしょう。
新入社員も、指示に疑問を感じたら、上司に確認するべきでした。
この「牛丼事件」は、私たちに重要な教訓を与えてくれます。それは、 **「指示待ち」と「忖度」の悪循環から脱却し、互いに責任ある行動をとることの重要性**です。
曖昧な表現や忖度に頼ることなく、自分の頭で考え、相手に明確な意思表示をすることが、より良いコミュニケーション、ひいてはより良い社会を築くための第一歩となるのではないでしょうか。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください
次のページ